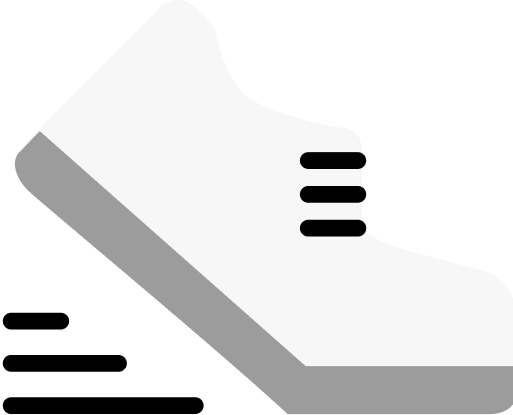役に立った
専門的な内容
実践したい
【アプリ限定】コラム評価で「スタンプ」が貯まる!
腸内環境の改善は健康の鍵。しかし、腸内環境には意外にも「お口のケア」が大きく関係していることをご存じですか?この記事では、腸とお口の関係に注目し、腸内環境を整えるための新しいアプローチをご紹介します。
腸の秘密
腸は消化・吸収だけでなく、免疫機能の約70%を担う重要な器官です。また、セロトニンといった「幸せホルモン」の生成にも関与し、精神的な健康にも影響を与えます。腸の表面積はテニスコート1面分に相当し、1,000種類以上、100兆個以上の細菌が生息しています。この細菌群は「腸内フローラ」と呼ばれ、腸内環境を左右する重要な要素です。腸内フローラのバランスを整えることで、病気予防や健康寿命の向上が期待できます。
人種、性別、年齢、生活習慣などにより、腸内細菌の内訳やバランスは一人ひとり異なり、同じ人でも、生活習慣や年齢によって、腸内細菌のバランスは変化します。
腸内細菌に関する研究は日々進んでおり、大腸がんや大腸ポリープなどの腸に関わる病気だけでなく、糖尿病やアレルギー疾患、自己免疫疾患など、様々な全身の病気との関わりも分かってきています。日頃から、腸内フローラのバランスを整え、良い腸内環境を保ち、病気予防・健康長寿を目指しましょう。
腸内フローラとは
腸内フローラとは、腸内に生息する細菌群のことで、従来、善玉菌:悪玉菌:日和見菌は「2:1:7」のバランスが良いと言われていました。乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は腸の健康を促進し、便通の改善や免疫力向上などの働きを持ちます。一方、悪玉菌は腸内環境を悪化させ、有害物質を生成して炎症や病気の原因となることがあります。しかし、近年研究が進んだことで、これまで良くも悪くもないとされていた日和見菌の中にも、人体に有用な菌が存在することが明らかになり、この分類は大きな意味をなさなくなりつつあります。良好な腸内環境に重要なことは、菌のバランスも重要ですが、それ以上に菌の多様性が重要であることが明らかになりつつあります。
腸内細菌のバランスは人種や性別、年齢、生活習慣によって異なり、同じ人でも生活習慣や加齢によって変化します。出生時には腸内は無菌状態ですが、出生後に細菌が腸内に住み始め、3〜5歳頃までにその人のベースとなる腸内フローラが形成されます。成人期には腸内フローラのバランスは比較的安定しますが、加齢やストレス、生活習慣の乱れなどによってバランスが崩れやすくなることがあります。腸内フローラの多様性が高いほど腸内環境は安定し、外部からの有害な影響にも強くなると言われています。そのため、腸内フローラのバランスを整えることは、健康を支える重要な鍵です。

※画像提供:株式会社サイキンソー(https://www.rakuten.co.jp/mykinso/)
腸活のすすめ
腸活とは、腸内環境を整えるための活動の総称です。腸活をすることで、便通の改善、免疫力の向上、肌の調子の改善、全身疾患、更にはメンタルヘルスの向上といった多くのメリットが期待できます。腸活の基本は、規則正しい生活とバランスの良い食事です。
特に、和食を中心とした食物繊維や発酵食品、オリゴ糖、レジスタントスターチを積極的に摂取しましょう。食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える働きがあります。また、納豆やヨーグルト、キムチといった発酵食品は、善玉菌そのものを摂取することができる優れた食品ですので、それらを一緒に摂ることが大切です。発酵食品は胃酸や加熱の影響を受けやすいため、食事で摂る時は、なるべく空腹時を避けることや、加熱のし過ぎなどに注意が必要です。また、外から摂取した菌は腸内に定着しづらい、という特徴があるため、継続的に摂ることも大切です。
さらに、ウォーキングや軽いジョギングなどの適度な運動、質の良い睡眠を十分にとることも腸活には欠かせません。運動は腸の蠕動(ぜんどう)運動を促進し、睡眠は腸内フローラのリズムを整えると言われています。
もう一つの大事な腸活「口腔ケア」
最近では「口腔ケア」が腸内環境を整えるための新しい視点として注目されています。厚生労働省の調査によると、日本人の2人に1人が歯周病であることが分かっています(※1)。口腔内には約700種類、数百億個の細菌が存在し、その中には腸内環境に影響を与える歯周病菌を含む「口内悪玉菌(※2)」があり、唾液や飲み物を介して腸内に到達すると、腸内フローラを乱す可能性があります。近年、口内悪玉菌(※2)が、腸内環境に影響を与えるという研究が発表されて話題となりました。2019年に行われた研究では、唾液と便から採取した菌の約3割がどちらからも検出されたと発表されました(※3)。口腔ケアを徹底することで、腸内環境への悪影響を防ぐことが期待されています。

うがい習慣と腸内環境についての調査
うがい習慣と腸内環境の関係を調べた調査結果があります。12名の被験者に対し、1日6回の水うがい(歯磨き含む)を1ヶ月間続けるよう指導したグループ(6名)と指導しないグループ(6名)に分け、1ヶ月後に腸内フローラ検査のための採便を実施しました。その結果、水うがいの習慣をつける指導をしたグループでは、腸内フローラの多様性スコアが上昇し、口内悪玉菌(プロテオバクテリア門やフソバクテリア門など)の占有率が低下、指導しないグループでは、大きな変化は見られませんでした。
<調査概要>
調査タイトル:うがい習慣による腸内フローラへの効果
調査実施:葛飾健診センター、株式会社サイキンソー
監修:医療法人社団さわやか済世 吉原一郎先生
調査内容:被験者12人を「うがい指導あり」と「うがい指導なし」の2群に分け、前者は「(歯磨き含み)1日6回の水うがい」を1ヶ月間実施。(後者は通常通りの生活。)1ヶ月後に腸内フローラ検査のための採便を実施。
この調査から、うがいによって唾液中の細菌量を減らし、腸内への悪玉菌の到達を減らすことができたと考えられます。

※グラフ提供:葛飾健診センター
腸内環境を整えるには、食事や運動に加え、口腔ケアも重要です。口腔内の健康を保つことで腸内フローラが整い、全身の健康に良い影響を与えます。口腔内の細菌が1番増えているのは起床直後です。歯磨きや水うがいに加え、朝1番にマウスウォッシュを活用することから始めてみてはいかがでしょうか。
監修

吉原一郎先生
医療法人社団さわやか済世 理事長 統括センター長
【略歴】
1993年 東海大学医学部卒
同年 日本医科大学第一病院内視鏡科入局
2000年 東京社会保険 葛飾健診センター 診療部長
2014年 医療法人社団 さわやか済世 葛飾健診センター センター長
2022年 現職
人間ドック健診指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本内科学会認定医、日本医師会認定産業医
※1…厚生労働省の令和4年(2022)「令和4年 歯科疾患実態調査」
※2…主な口内の悪玉菌は、虫歯の原因となるミュータンス菌や、歯周病の原因となるジンジバリス菌(P.g.菌)などが挙げられる。
※3….Elife.2019Feb12;8:e42693.